
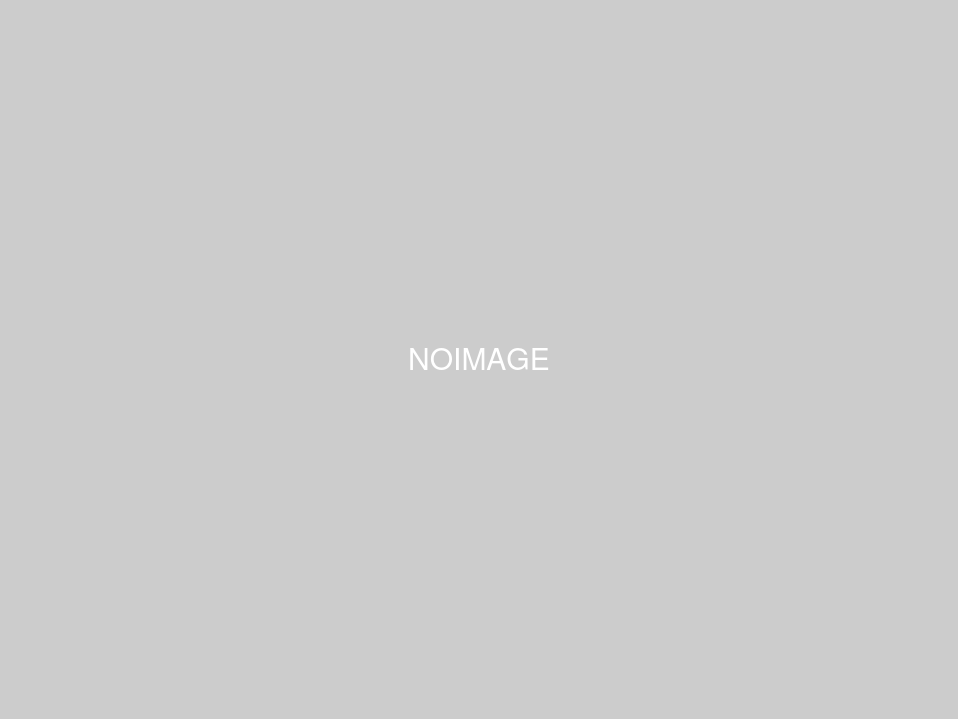


- 真上
- 横
- 花芽
- 花芽 (アップ)
Echeveria derenbergii(エケベリア・デレンベルギー)
― 日本名「静夜(せいや)」 ―
① 原種概要
エケベリア・デレンベルギーは、ベンケイソウ科エケベリア属に属する小型原種です。青緑色の整ったロゼットと、冬から春にかけて咲く黄色い花が魅力で、世界中で広く栽培されています。
日本では 「静夜(せいや)」 の名前で古くから親しまれ、多肉植物愛好家にとってクラシックな代表種のひとつです。
② 名前の由来と読み方
学名 Echeveria derenbergii の「derenbergii」は、19世紀ヨーロッパの園芸家 Derenberg 氏への献名と考えられています。
日本では「デレンベルギー」と音写されますが、園芸では 「静夜」 の呼称が一般的です。
③ 葉姿・色彩の特徴
葉は小型で肉厚なスプーン型。青緑色を基調とし、うっすらと白粉をまといます。寒さにあたると葉先が赤く染まり、群生すると色彩のコントラストがより美しくなります。ロゼットは端整で、鉢一杯に広がる群生株の姿は観賞価値が高いです。
④ 原産地と自生環境
メキシコ中部の標高が高い乾燥地帯に自生しています。強い日射しと昼夜の寒暖差がある環境に適応し、葉に水分を蓄えることで生き残ります。
⑤ 起源と分類史
19世紀後半にヨーロッパに導入され、当初は Echeveria elegans や E. pumila と混同されることもありました。花の形態(黄色に赤を帯びる鐘形の花)や葉の配列によって区別され、20世紀には独立種として整理されました。現在では「小型群生型エケベリア」の代表格とされています。
⑥ 季節による色の変化
夏は青緑の色合いを保ちますが、秋から冬には葉先が赤みを帯びます。特に寒さと日照が合わさると鮮やかな紅葉を見せ、冬の静夜は群生株ほど華やかさを増します。
⑦ 花の特徴
冬から春にかけて花茎を伸ばし、黄色く光沢のある花を咲かせます。外側が赤を帯びる花弁はロウ細工のようで、群生株が一斉に咲くと華やかな景観になります。
⑧ 栽培の魅力
静夜は丈夫で育てやすく、初心者にもおすすめできる原種です。子株を多く吹くため群生しやすく、鉢全体を覆うコロニー状の姿に仕立てられます。クラシックな多肉として、シンプルながらも存在感があります。
⑨ 繁殖の課題と方法
葉挿し・挿し木ともに成功率が高く、株分けによる増殖も容易です。実生繁殖も可能で、交配親としても利用価値がありますが、他種との識別が課題となることもあります。
⑩ 有名な交配種 ― 「ローラ」
静夜は交配親としても重要な役割を果たしました。特に有名なのが 「ローラ」 です。
ローラ (Echeveria derenbergii × E. elegans)
丸みを帯びたロゼットと美しい粉白色の葉を持ち、エケベリアの園芸種の中でも屈指の人気品種です。静夜の群生性と可愛らしさ、エレガンスの端正なフォルムが融合した名品として世界中で愛されています。
⑪ 日本での流通史
日本には明治期以降に導入され、戦前から「静夜」の名で普及しました。昭和の園芸ブームでも定番品種として扱われ、現在でも多肉植物愛好家の間で広く栽培されています。ローラをはじめとした交配種の存在もあり、クラシックな原種としての地位は揺るぎません。
⑫ むらさき園からの栽培メモ
むらさき園でも静夜は大切にしている原種のひとつです。冬の低温期にうっすらと紅葉し、むらさき園では実生からは爪先の赤みが強い個体も生まれてきていて、黄色い花が咲くと温室が華やかに彩られます。群生株は見応えがあり、お客様にも人気です。交配親としてのポテンシャルも高く、ローラの存在はその魅力を象徴しています。夏の蒸れ対策さえ注意すれば、長く安定して楽しめる品種ですが、実生からの個体によっては冬の寒さが厳しい時には溶けることもあった
